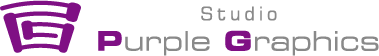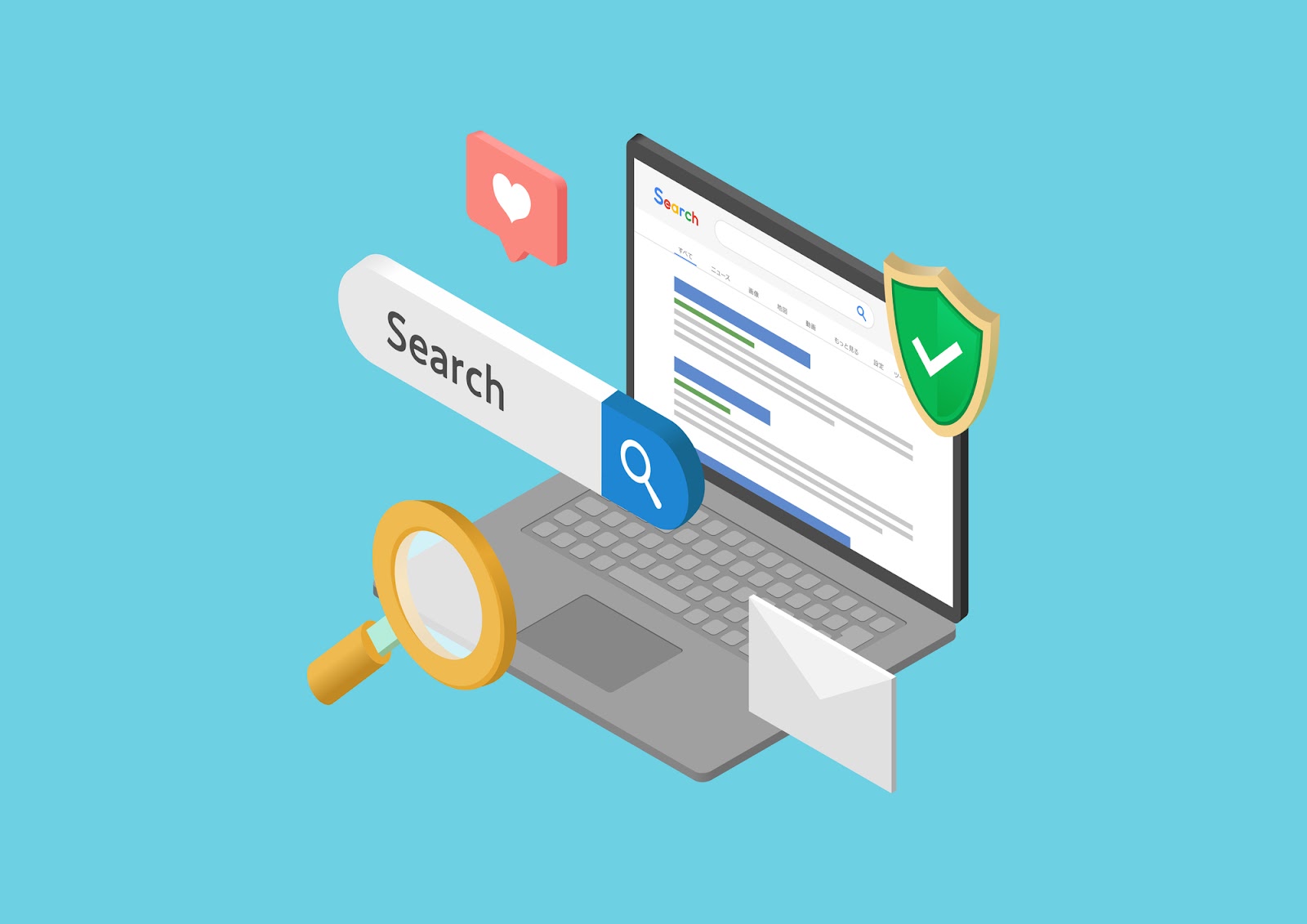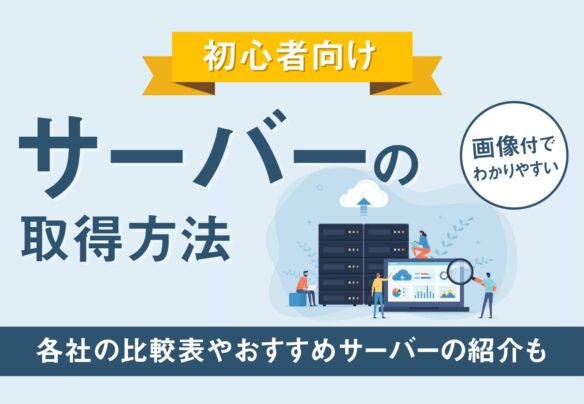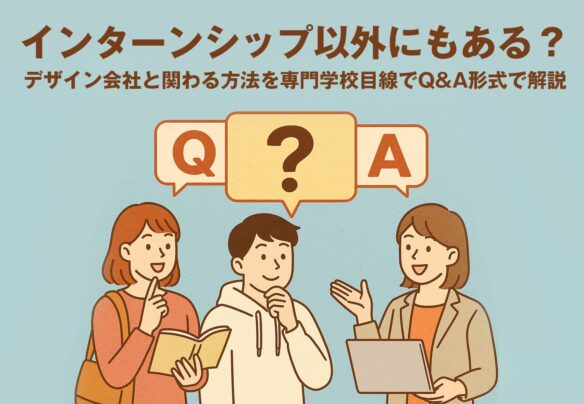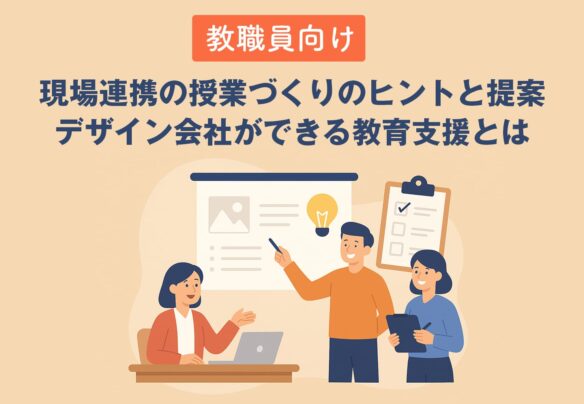本記事について
このような方におすすめ
- SEOについての基本を知りたい
- ホームページの検索順位を上げたい
- 最新のSEOトレンドに対応したい
- 広告費を抑えながら安定した集客をしたい
記事を読む価値
SEO対策の基礎から具体的な施策方法をわかりやすく解説いたします。
この記事を読み進めることで、誰でもSEO対策の基礎を理解できるようになります。
本記事の信頼性
当記事は、大阪のホームページ制作会社パープルグラフィックスが監修・執筆しています。
弊社は2010年9月に設立して以来、10年以上もこの業界で数多くのホームページ制作とSEO対策をしてまいりました。
そんなホームページ制作会社の担当者自らが、SEO対策の基礎から最新の情報までを、初心者の方にもわかりやすくご説明いたします。
SEOとは
SEOとは、「Search Engine Optimization」(検索エンジン最適化)の略称であり、ホームページをGoogleやYahoo等の検索エンジン上でより上位に表示させるためのテクニックのことを呼びます。
具体的には、Googleの検索エンジンがどのようにコンテンツをクロール(ホームページ内を巡回してチェックすること)して、インデックス(検索エンジンに登録されること)して、順位付けするかを理解して、そのアルゴリズムに基づいてホームページを最適化することで、検索エンジン上での表示順位を向上させることが目的となります。
SEOは以下のような施策の組み合わせで成り立っています。
- 上位表示させたいキーワードの設計
- タイトルやディスクリプションなどメタ情報の最適化
- コンテンツの質や構造の見直し
- 内部リンクの整理
- 信頼性の高い外部リンクの獲得
- モバイル・表示速度・UXなど技術的な改善
2025年現在では、検索エンジンがコンテンツの「本質的な価値」をより重視するようになっており、「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」に基づいた対策がますます重要となっています。
SEO対策の基礎知識
SEO対策について知っておくべき基礎知識をいくつか紹介します。
Googleは世界で最も多くの利用されている検索エンジン
Googleは世界で最も多くの検索ユーザーに利用されているため、Googleのアルゴリズムに適合するSEO対策が重要というわけです。
中には、普段Googleは使わず、Yahooで検索されている方も大勢いらっしゃるかと思いますが、実は、YahooもGoogleのアルゴリズムを利用して検索結果を表示させているので、結局はGoogleを意識する必要があるというわけです。
Googleの検索エンジンのアルゴリズムを理解することが必須
Googleの検索エンジンは、「アルゴリズム」と呼ばれるルールに基づき、ホームページを評価して検索時の順位を決定しています。つまり、検索順位を上げるためには、Googleのアルゴリズムを理解し、それに適合するSEO対策を行う必要があるということです。
ホームページのコンテンツの品質が重要
Googleの検索エンジンは、ホームページ上のコンテンツの品質を評価します。
当たり前のことではありますが、より質の高いコンテンツを提供することが、検索エンジンの順位を上げることに繋がります。
キーワードの選定が重要
ホームページを作るには、当然書きたい記事(内容)があるわけですが、それを一般のユーザーはどんなキーワードで検索してここへたどり着くのか、そしてどんな悩みがあって、どんな答えを求めてやってくるのかを、考えながら作っていく必要があります。
検索順位を上げるということは、こういうニーズが前提にあることを考えて設計する必要があります。
リンクが重要
ホームページの信頼性を高めるために、外部サイトからのリンクを獲得することが重要です。
これを「外部リンク」と呼びますが、一つのホームページ上にあるページ同士を上手にリンクで繋ぐことも重要となります。これを「内部リンク」と呼びます。
読者にとって必要なリンク構造を貼って、且つそのテキストリンク内にキーワードを含めることで、Googleのロボットはホームページ内をより理解しながら巡回することができるわけです。
SEO対策のメリット
SEO対策を行うことで、以下のようなメリットが得られます。
ホームページのアクセス数が増える
SEO対策によって、検索エンジン上での表示順位を向上させることができるため、ホームページへのアクセス数が増えます。アクセス数が増えることで、ビジネスやブランド認知を向上させたり、ホームページ上での売上をUPさせることができます。
ターゲットユーザーにアプローチしやすくなる
SEO対策を行うことで、特定のキーワードやフレーズに関連するコンテンツが検索エンジン上で上位に表示されるため、ターゲットとするユーザーにアプローチしやすくなります。
リスティング広告に比べてコストパフォーマンスが高い
SEO対策は、リスティング広告などと比べて圧倒的に低コストで行うことができます。
検索上位表示させるもう一つの手段として、リスティング広告などがありますが、こちらは課金によって上位表示を行います。したがって、リスティング広告は課金をストップした途端に検索結果から姿を消してしまいます。
一方、SEO対策による検索上位表示は、順位が上がるまでは時間もかかり苦労しますが、その後もご自身の財産となる(※)というところがSEOの特徴になります。
※Googleのアルゴリズムは日々進化するため、SEO対策を長期間怠ると、SEO対策をし続けている競合に追い抜かれてしまうため、放置して良いという意味ではありません。
SEOで検索順位が決まる仕組み
検索順位が決まる仕組みは、検索エンジンのアルゴリズムによって決まります。
検索エンジンは、クローラーと呼ばれるプログラムを使って、ホームページをインデックス(登録)し、独自のアルゴリズムによってホームページを評価して、検索結果の順位を決定します。
ではそのアルゴリズムについて代表的な4つをご紹介します。
コンテンツの質(検索キーワードとの関連性)
検索ユーザーが検索クエリに入力したキーワードと、実際のホームページのコンテンツがどれくらいマッチしているかが、順位に影響します。
また、そのコンテンツそのものが、検索ユーザーの求める情報をしっかりと提供できているか(ユーザーのニーズに応えられているか)が重要となります。
仮にタイトルやディスクリプションが魅力的で、ユーザーからクリックをされたとしても、実際の内容の品質が低ければ、ユーザーはすぐに離脱し、他のホームページを探すために再検索を行うでしょう。
でも実は、これらのユーザー行動はGoogleにしっかりと観られていて、減点対象となります。
評価を下げられないためにも、ホームページ上でユーザーの問題を解決してあげられるようなコンテンツを用意することが重要となります。
被リンク(ページの信頼性)
被リンクとは、外部のホームページから自分のホームページへリンクを貼られることを指します。
シンプルな考え方としては、他者から引用されたり紹介されるということは、有益なホームページなのであろう、という評価の仕方です。以前に比べてSEOにおける被リンクの重要度は下がりましたが、それでもまだまだ重要な要素といえます。
自作自演などの悪質な被リンクはマイナス評価に繋がりますが、以下のような有益な被リンクは、特にプラスに働きます。
- ページランク(※)の高いホームページからの被リンク
- 関連性の高いホームページからの被リンク
※Googleは、それぞれのホームページを独自にランク付けしており、そのホームページのランクが高い程、被リンクの価値も高くなります。
サイト設計
ホームページのコンセプトやテーマのことです。
色んなテーマの記事を扱いすぎて、結局何のホームページか、何のページかわからないホームページよりも、テーマに一貫性のある特化型のホームページの方が良いとされています。
これは、後述するE-E-A-Tという指標における「Expertise(専門性)」に通じることになります。
その他
ユーザー行動
ユーザーがどう行動したかという実際の反響も、後々検索順位に返ってきます。
具体的には、主に以下の行動が挙げられます。
- 検索結果に表示されてから訪れるまでのクリック率
- ホームページに訪れてからの滞在時間
- ホームページ上でのユーザー行動(どこまでスクロールして、どのボタンを押して、どのページへ遷移するか等)
- いつどこでユーザーが去っていくか
これらのユーザー行動によって、検索キーワードとどれくらいマッチしているか、ユーザーが満足いくコンテンツが用意されているか、ユーザーが次のアクションを起こしたくなる魅力があるか、などの点をチェックされます。
モバイルフレンドリー
スマホの普及率が上がった今、ホームページはスマホで閲覧した際に、しっかりと読みやすい文字サイズとなっているか、ボタンが指で押せるサイズや位置にあるか等を細かくチェックされています。これらのチェックリストをクリアできているホームページは、検索エンジンから「モバイルフレンドリー」として認識されて、品質が高いと判断されます。
SEOにおける検索意図とキーワード選定
SEOにおいて、ユーザーの「検索意図(インテント)」を的確に捉えることは、2025年の今、最重要ポイントとなっています。
検索意図とは?
検索意図とは、ユーザーが検索行動を起こした背景や、最終的に知りたいこと・得たいことを指します。
たとえば…
- 「ホームページ 制作 相場」→ 金額を知りたい
- 「整体院 集客 方法」→ 集客の具体策を探している
- 「工務店 SEO 成功事例」→ 他社の成果を参考にしたい
これらの検索意図を読み取った上で、ニーズを満たすページを設計することが求められます。
キーワード選定のポイント
2025年現在、GoogleのAIは単なるキーワードの出現頻度ではなく、「文脈と意味」を理解する精度が高まっています。そのため、下記のような観点での選定が重要です。
- ロングテールキーワードの活用(例:「大阪 工務店 SEO」など)
- ペルソナ視点でのニーズ把握
- 検索ボリュームだけでなく、成約率も意識
- 競合サイトと比較した差別化軸の明確化
キーワードありきではなく、「ユーザー視点のコンテンツ設計」が結果的にSEOにも好影響を与えます。
SEO対策の種類
SEOは、大きく「内部対策」「外部対策」「コンテンツ対策」に分類されます。それぞれの意味と役割について、2025年の最新動向を踏まえて解説します。
内部SEO対策
内部対策とは、自社のWebサイト内の構造や記述ルールを、検索エンジンにとってわかりやすく整理する施策です。
- メタタグ(タイトル・ディスクリプションなど)の最適化
- H1〜H3などの見出し構成の整理
- モバイル対応(モバイルフレンドリー)
- サイトの表示速度改善
- サイトマップ・パンくずリストの設置
- 構造化データ(Schema.org)のマークアップ
特に2025年現在では、Googleがユーザー体験(UX)を重視するようになっており、表示スピード・スマホ最適化・アクセシビリティなどの要素がSEO評価にも強く影響します。
適切なキーワードの選定
検索ユーザーがよく検索するキーワードを選定し、ホームページ内で適切に使用することがSEO対策の基本です。
選定したキーワードを、後述するタイトルタグやメタディスクリプション、コンテンツ内に適切に配置することで、検索エンジンに対する信頼性を高め、検索順位を上げることができます。
ページ内でキーワードを程よく使用することは、キーワード対策として有効ですが、不自然にやりすぎてしまうと返ってペナルティを受けてしまうことになります。
ユーザーが読んでいて、不自然に感じないような出現率をめざしましょう。
タイトル・ディスクリプションの最適化
メタデータ(タイトルタグ、メタディスクリプション等)は、検索エンジンにとって非常に重要な情報源となります。適切なタイトルタグやメタディスクリプションを設定することで、検索エンジンにとってホームページの内容をより正確に理解させることができ、ランキングの向上につながります。
タイトル・ディスクリプションの効果的な書き方については、以下の記事で詳しく解説しております。
見出し(hタグ)の適切な使用
少々専門的な話題になってしまいますが、通常、見出しには「h1」や「h2」などのタグを、表では見えないところで使用しています。
※『h』はheading(見出し)の略です。
これらのタグを用いた見出しは、本文よりもさらにキーワードの内容を着目・評価されることになります。
したがって、見出しはコンテンツを表す内容にすると共に、どうキーワードを盛り込むかを慎重に考えて考案する必要があるというわけです。
h1…ページの大見出しで、基本的に1ページに1つのみを設定します。特別な理由がなければ、そのページのタイトルをそのまま設定して構いません。
h2…ページの中見出しで、いわゆる目次に掲載される項目名ですが、このチョイスが重要です。他のSEO上位サイトがどのようなh2見出しを使用しているか、競合調査を行い、設定することが大切です。
高品質なコンテンツ(E-E-A-T)を用意する
先述したように、そもそもユーザーにとって有益な情報を提供する必要があります。
したがって、内容やボリュームの薄いページで上位表示を狙うのは難しいといえます。
質はもちろんですが、網羅性という意味でも最低限のページ数(コンテンツ量)を用意する必要があるでしょう。
品質を評価する指標としては、後述するE-E-A-Tという考え方があります。
内部リンクの設定
内部リンクの最適化とは、ホームページ内のページを行き来するためのリンクを正しく設定することを指します。
適切なアンカーテキストを使用することで、検索エンジンにとってホームページの内容を正確に理解させることができます。また、ユーザーもその内部リンクを辿ってストレスなくサイト内を移動できるため、サイト滞在時間も長くなり、これらすべてがSEOの向上に役立ちます。
リンクを貼る際は、遷移先のページを表すキーワードを含めることがコツです。
サイトマップの設置
ホームページの全ページを一覧できるようにしたXMLファイルのことです。
サイトマップは、ホームページの構造を示しているため、検索エンジンがホームページ内を正しくクロールされて、しっかりインデックスされるのに役立ちます。
ページの読み込み速度の改善
ユーザーファーストという観点から、読み込み速度についてはGoogleから厳しくチェックされます。
最もウエイトを占めるのが画像ですが、入手した画像をそのまま使ったりせず、必要最低限のサイズにリサイズすることが必要で、他には画像を圧縮して容量を軽くしてから使用したり、Webp等の次世代画像形式にするといった工夫が必要になります。
重複コンテンツをなくす
Googleは重複コンテンツを嫌います。
そこで、最初に行うべき重複コンテンツ対策は、「URLの正規化」です。
URLの正規化とは、同じページを示す複数のURLが存在する場合に、それらを1つの正しいURLに統合することをいいます。
例)「index.htmlのあり・なし」「wwwのあり・なし」「httpsかhttpか」等
「URLの正規化」以外にも、ホームページ内に同じようなことを書いているページが複数あると、重複コンテンツ扱い見なされる可能性があります。
似た内容のページを複数あると、Googleとしては「●●●という検索ニーズに対して一体どちらのページを検索結果に出せば良いのか…?」と迷ってしまい、日によって異なるページが表示されたり、複数並んで表示されたりすることになります。
そうなるとユーザーからのアクセスが分散されたり、Googleからの評価を食い合うカニバリズムという現象が起きたり、そもそも重複コンテンツはマイナス評価になりますので、最悪の場合どちらの順位も下がってしまうというマイナスな結果に繋がってしまいます。
1ページ1キーワード
「1ページ1キーワード」とは、1つのページに対して、1つのキーワードに焦点を絞ってコンテンツを作成しましょう、という考え方です。
例えば、「英会話教室」というキーワードを狙いたいページにおいて、「サッカー教室」や「健康食品」等の、複数のキーワードを使って情報を掲載すると、検索エンジンにとってどのキーワードにフォーカスすべきかが明確になりません。
しかし、「英会話教室」というキーワードに焦点を絞り、そのキーワードに関連する情報を掲載することで、そのページが「英会話教室」に関するページであると評価されて、結果的に検索結果で上位に表示される可能性が高まるというわけです。
情報の新しさ
Googleの検索エンジンは最新情報を提供できるサイトを優先的に表示しようとします。
したがって、新しいコンテンツを生むことはプラスになりますが、それだけではなく、過去に作成した記事であっても、内容を見直して情報をアップデートすることで評価UPに繋がります。
コラム記事であれば、記事を更新した後に更新日時も最新の日付に変更して、常にホームページの情報が新鮮である旨をアピールしましょう。
外部SEO対策
外部対策とは、他の信頼性あるWebサイトから被リンクを得ることで、自社サイトの「評価」を高める施策です。
- 被リンク(バックリンク)獲得
- サイテーション(ブランド名や住所の言及)
- SNSでのシェア・拡散
- 業界ポータルやメディアからの紹介
なお、2025年現在では過剰な相互リンクやリンク集登録などの不自然な外部施策はペナルティの対象になるため、自然なリンク獲得が求められます。
コンテンツ対策
コンテンツ対策とは、ユーザーにとって価値のあるページ内容(記事・商品情報・事例など)を作ることです。
検索エンジンは、以下のような視点でコンテンツを評価しています:
- 検索意図を満たしているか
- オリジナリティ・網羅性があるか
- 専門性・信頼性があるか(E-E-A-T)
- 定期的に更新されているか
2025年のトレンドでは、単なる長文記事よりも、検索意図を的確に捉えたコンパクトで質の高いコンテンツが評価されやすくなっています。
E-E-A-Tとは
E-E-A-Tとは、Googleが検索結果の品質を評価するための指標の1つで、以下の4つの要素から構成されます。
- Experience(経験・体験)
- Expertise(専門性)
- Authority(権威性)
- Trustworthiness(信頼性)
E-E-A-Tについては以下の記事で詳しく解説しております。
このように、ホームページのコンテンツの品質を評価する際に、専門性、権威性、信頼性、そして経験の4つの要素を総合的に評価する指標が、E-E-A-Tです。
E-E-A-Tの重要性は、特にお金や医療などの分野で高いといわれており、これらのホームページを運営している方は特に注意が必要です。
YMYLとは
YMYLは、Your Money or Your Lifeの略称で、Googleが定めたコンテンツの品質評価ガイドラインの1つです。
Googleは、ユーザー財産や健康、生活に影響を及ぼす可能性があるホームページに対して、特に高い品質の要求を設けています。YMYLに含まれる分野としては、金融、医療、健康、法律などが挙げられます。
これらの分野に関連するホームページには、高い専門性、正確性、信頼性、そして実際の経験・体験に基づく情報が求められ、適切な情報源や著者の詳細な情報などが必要とされます。これが先述したE-E-A-Tです。
したがって、YMYL領域のホームページでは、特にE-E-A-Tを意識したコンテンツ作りが求められているというわけです。
YMYLについては以下の記事で詳しく解説しております。
SEOとリスティング広告の違い
SEOと混同されやすいのが、リスティング広告(Google広告)です。違いを整理しておきましょう。
| 比較項目 | SEO(自然検索) | リスティング広告(有料) |
|---|---|---|
| 表示順位 | 検索エンジンの評価で決定 | 入札金額+品質スコアで決定 |
| 費用 | クリックに費用は発生しない | クリックごとに費用が発生 |
| 即効性 | 運用には中長期的な時間が必要 | 即日から効果が出る可能性あり |
| 資産性 | コンテンツが資産として残る | 配信停止=表示されなくなる |
SEOは長期的に安定した集客を目指す施策であり、広告に頼らず成果を出したい中小企業・教育機関などに最適です。
まとめ|2025年のSEOは「ユーザー中心設計」がカギ
SEOとは、「検索順位を上げるためのテクニック」ではなく、「ユーザーの検索意図に応えるための仕組みづくり」です。
2025年のSEOでは、以下の要素がより重視されるようになっています:
- 検索意図に合った質の高いコンテンツ
- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の構築
- スマホ最適化・高速表示などの技術対応
- 自然なリンク獲得と信頼される運用体制
パープルグラフィックスでは、SEOの基本設計からキーワード選定・記事制作・運用改善まで一貫してご支援が可能です。
「SEOをやってみたいけど、何から始めればよいかわからない」という方も、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
大阪のパープルグラフィックスは、ホームページ制作からSEO対策までを一貫して請け負っています。
自社サイトの順位を上げたい方や、これからホームページを立ち上げたい方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。